
『学び合い』は互いの「分からない」を学び合おうとする行為が軸

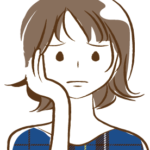
こんにちは、COTECHI です。
『学び合い』は、子供が関わり合うことに、真の学びがあるとして、大切にしますが、具体的にどういうことなのですか?

『学び合い』は、子供同士が関わり合うことを目指しますが、それは、子供相互に関わりが生まれれば、それだけでよいということではありませんよ。
大切なのは、その子供同士の関わりが、真の『学び合い』になっているかどうかということなのです。
教師は、そこを見取っていかないと、ペア学習やグループ学習が、単に、雑談の場になりかねません。
ですから、子供同士の活発な関わり合いの姿が生まれると、私の関心は、その子供同士の関わりの内容に向くことになるのです。

グループでの子供たちの様子を見ていて、それは、初めはこうなってしまうな、でもここからどう関わり合いの中身を充実させていくか、それが『学び合い』へ導く鍵になるんだよね。
そういう意味では、これ( グループ学習が雑談の場になってしまうこと)は、先生たち、だれもが通る関所のようなものなのだと感じたことがあります。

それは、子供たちの関わりが、真の『学び合い』として関わっているではなく、「教え合い」という行為になっているのみ・・・ということですね。
目次 [hide]
「教え合い」と『学び合い』の違い
「教え合い」と『学び合い』の考え方、表出される子供の姿の違いについては、『「学び合う学び」が生まれるとき』(世織書房)によると、要するに、よく分かっている子供がそうでない子供に教えるのが「教え合い」であることであります。
その反対に、分からない子供が、援助を求めて、それに他の子供が応じるのが『学び合い』だと、考えたいのです。
「教え合い」は、理解できている子供が、まだそこに至っていない子供に、一方向に教えることが軸となっているのですが、『学び合い』は、「分からないことを互いに学ぼうとする行為」が軸になっているのだと考えたいわけです。
つまり、理解できている児童にとっても、理解できていない児童がどういうところでつまずいて、理解に至らないかを、その児童から学びを得ている状態が好ましいのです。
「学び合う学び」では、「教え合い」ではなく、『学び合い』が好ましいと思うのです。
『学び合い』において大切にすべき「互恵的関係」

学級の子供たちは、とても積極的に子供同士が関わり合っているように見える学級があります。
けれども、すでに問題が解け、課題の結果を自分のものとできている子供が、課題解決の方法や課題解決の見通しを持てていないで、困っている子供に、単にその解き方を教えてあげるといった状態に陥っている様子をよく目にします。
できている子供が、できていない子供の面倒を見ている・・・という状態です。
それはそれで、自分は、分かったのだから友だちであるAさんも、Bくんにも分かるようにしなければ・・・という意欲の表れで、その子供たちの意欲を否定してはいけませんし、その行為自体は、間違っているとは思いません。
しかし、これは、「教え合い」です。
これでは、私が重要だと言っている『学び合い』において、大切な「互恵的関係」は生まれてはきません。
互いに関わり合ってよかったと思える関係づくり

それは、『学び合い』において、関わり合ってよかったと思う時には、必ず、互いにそうしてよかった、関わり合って心地よかった、と思える事実・感情が生まれるからです。
そうした感情がなくて、学習課題が解決できて、理解できている子供から、まだ理解に及んでいない子供に、一方向に「教える」「教えてあげる」という行為では、双方に、「真の学び」が生まれないのではないかと考えるわけです。
ですから、私は、それでは、よしとするわけにはいかないのです。
つまり、『学び合い』における友達関係、人間関係の肝は、その課題は、「教え合いから学び合いへ」というペア、グループの学びへの転換だと思うのです。
『学び合い』とは、友だちの「生き方」を学び合う行為
日本では「勉強=苦しみ」のイメージが強いように感じます。
知らず知らずのうちに、学ぶ目的を「良い大学に入って、良い会社に就職するため」と捉えている人が多いのではないでしょうか。
これは「生き方を一つに絞ってしまっている」ように思います。
人それぞれ個性や得意なことが違うのに、本当にたった一つの生き方に絞ってしまっていいのでしょうか。
人によって学ぶペースには差があり、興味の対象も異なります。
「競争しなくてもいい環境」・「人より上でも下でもなく、みんなが対等な関係でいられる環境」で学ぶことはとても大切だと思います。
子どもたちの『学び合う』行為は、私に「先生自身も学ぶ立場であること」、「人はどのポジションにいても、何歳であっても、常に成長過程であり、学ぶ姿勢を忘れてはいけない」ということを教えてくれました。
今では仕事と勉強、常に並行して行っています。
そうすることで、知識もアップデートできますし、先生との対話や他の生徒との交流なども楽しめ、気持ち的にもリフレッシュできます。
教室での学習もそうあるべきです。
国語や算数などの教材を材料として、互いにどのように学ぶと楽しいのかの「生き様を見せ合う場」だと思うのです。
「あの子の説明の仕方はわかりやすいな。」「とっても丁寧に教えてくれて、私もそういう人になりたいな。」・・などと学習を通して、どのように学習をしていくとよいのか、どのような学習行為、ひいては生き方が素敵なのか、マネしたくなるような「生き様」の見せ合い、「憧れ合い」だとと思うのです。
ですから必然的に先生の目は子どもたちのそうした行動、行為に注目して、そうした児童の行動を価値づけていくことが教師の役割になっていくのです。
まさしく「ティーチング」ではなく「コーチング」となるわけですね。
現実的には、現在も未来も、全ての人々、だれもがお金をたくさん持っている訳ではないし、豊かな生活ではないかもしれませんが、とても楽しそうに暮らしていけることを求めたいのです。

その理由の一つとして、これからは、ますます経済的に苦しい時は「助け合う」ということが、当然の様になされていくことが大切な時代に入っていくと思うからです。
無理にひとりで経済的に自立しなくても、家族同士で助け合うことで、仲間同士で助け合うことで、「自分達でセーフティーネットを作りあげる」ことができることを学んで欲しいのです。
人は無理に自立しようとすることで、周囲の人との助け合いの関係性が少なくなり、人との繋がりが減ってしまい、結果的に「孤立」してしまうこともあります。
物質的には豊かではないかもしれませんが、人と人との温かなつながりや笑顔、そして互いに楽しむ精神を豊かにしていくことが、人としての幸せに繋がることの基礎であることを、小さい時から学ばせてあげたいです。

.png)
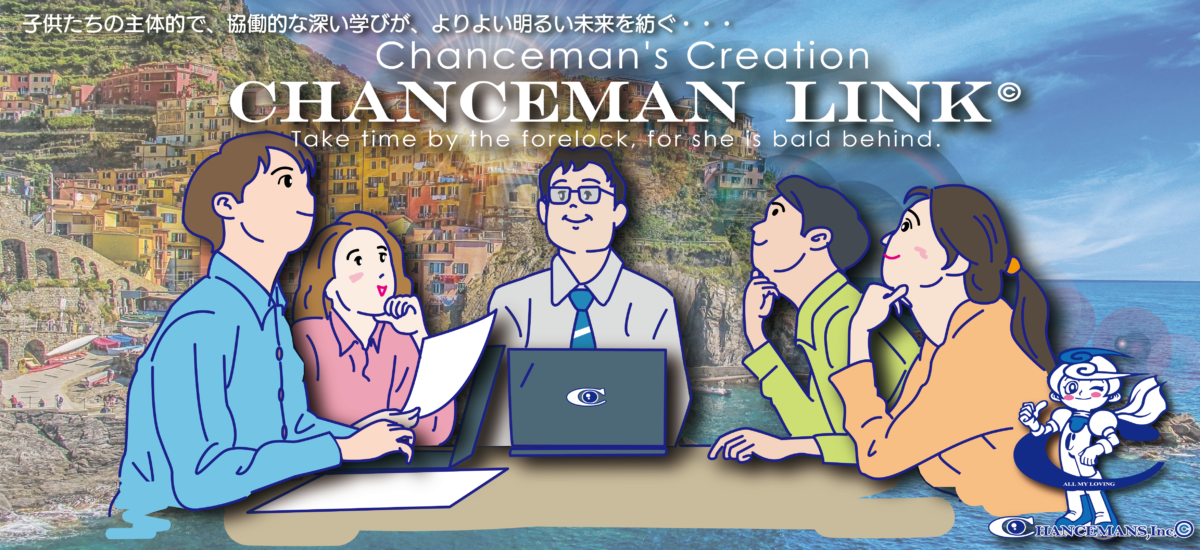

























.webp)