
この記事を読むのにかかる時間: 2 分

![P-MASTER]()
![P-MASTER]()
![]()

COTECHI
「最近の子どもは失敗を恐れる」と、教育現場の先生やスポーツのコーチなど、普段子どもと接する機会の多い人であれば肌で感じているそうですが・・・。
なぜ、子どもは失敗を恐れるのでしょうか?

P-MASTER
そうですね・・・職場でも、「初めから正解を知りたがる」「自分に与えられた仕事以外に手を出さない」といった新入社員の行動が目立ち、最近の若者は失敗を恐れるようになったと感じる方も多いのではないでしょうか。

P-MASTER
大事なのは「失敗しないこと」ではありません。
子どもを大切に思うあまりに、あれこれ先回りして親が手を出してしまうのも、成長を阻害する原因となります。
親が子どもの障害を取り除き、失敗しないよう育てた場合、子どもに社会の逆境に立ち向かえる力は備わっているでしょうか?
目次
子どものうちに「失敗に対する免疫力」をつける

ひとりっ子家庭と兄弟がいる家庭の決定的な違い
これが、第2子以降の子どもだと、兄や姉が失敗するところを見ており、「あれをやるとお父さんから怒られちゃうんだ」などと疑似体験ができています。 しかし、ひとりっ子は、同年代の失敗を家で目にすることはほぼありません。 だから、失敗についてわかっておらず、するときには大きな失敗になったりします。 とくに女の子の場合、大きい失敗はネガティブに働くので、小さい失敗をたくさん経験して免疫力をつけておくことが大事です。 中学受験も、ピアノの発表会も、サッカーの試合も、いきなり本番に臨ませるのではなく、失敗も含めた小さな体験を前もって積ませてあげましょう。 小さな失敗を重ねることが成功につながります。今日は「負ける練習」をしたんだ!
『受け身・負ける練習』相田みつを
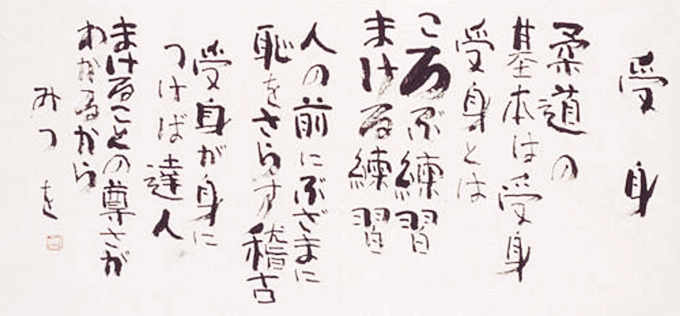
みんなで受け身の達人になろう。そして、黒帯になろう。

.png)
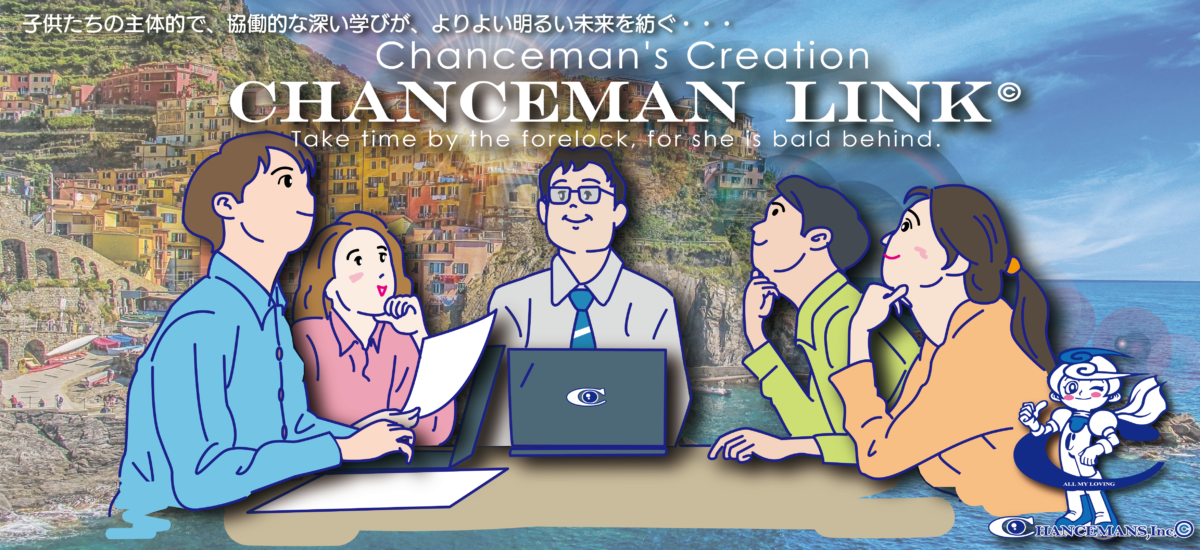


























.webp)